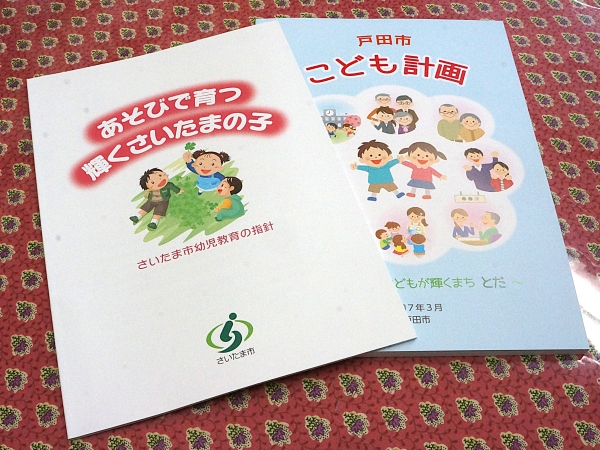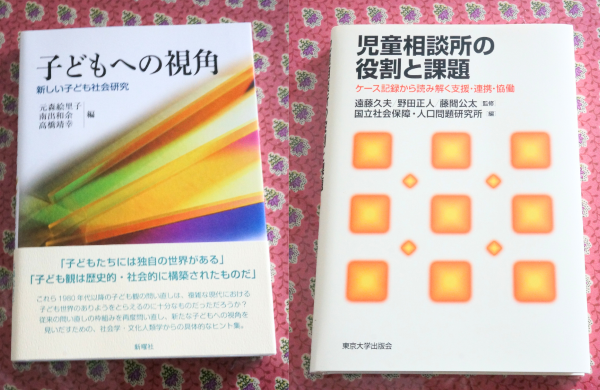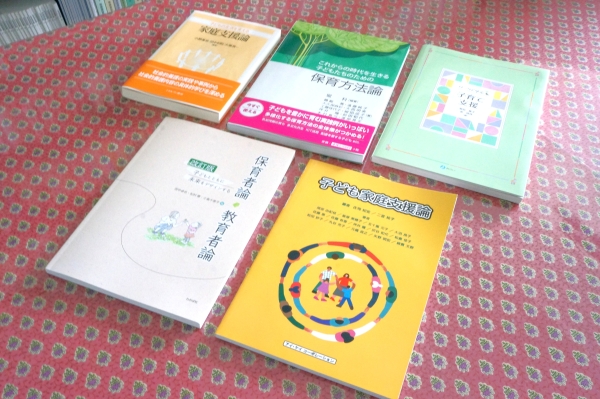先生に聞く─東京成徳の研究紹介─ 坪井瞳教授
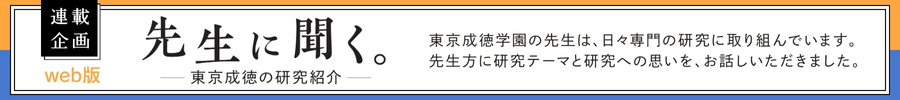
2025年7月20日
本記事は、東京成徳学園広報誌「TOKYO SEITOKU NOW」との連動企画です。
広報誌に掲載した誌面も、ぜひあわせてご覧ください(誌面は【こちら】)。
広報誌に掲載した誌面も、ぜひあわせてご覧ください(誌面は【こちら】)。
坪井 瞳 教授
今回「東京成徳の研究紹介」としてご紹介するのは、東京成徳大学子ども学部の教授 坪井 瞳(つぼい ひとみ)先生です。
坪井先生は、保育の場における「支援を必要とする家庭で育つ子ども」に対する支援の実態とその在り方について研究をしています。
坪井先生は、保育の場における「支援を必要とする家庭で育つ子ども」に対する支援の実態とその在り方について研究をしています。
経歴等について
大妻女子大学家政学部児童学科卒業、大妻女子大学大学院修士課程修了、博士後期課程単位取得退学。
大学院生時代に、お茶の水女子大学附属幼稚園に2年間勤務、その後荒川区子ども家庭支援センター(現・荒川区児童相談所)で児童虐待相談・養育相談等の相談業務に携わりました。
その後、いくつかの大学で専任教員として保育者・教員養成に携わり、現在の東京成徳大学は着任から9年目となります。
大学院生時代に、お茶の水女子大学附属幼稚園に2年間勤務、その後荒川区子ども家庭支援センター(現・荒川区児童相談所)で児童虐待相談・養育相談等の相談業務に携わりました。
その後、いくつかの大学で専任教員として保育者・教員養成に携わり、現在の東京成徳大学は着任から9年目となります。
大学以外に、行政にも関わりを持ち、さいたま市巡回保育相談員、さいたま市・世田谷区幼児教育アドバイザー、世田谷区地域保健福祉審議会、戸田市児童福祉審議会会長など、基礎自治体での子どもに関する相談業務、保育者・教員の人材育成・研修、事業計画、教育や福祉の方針作成に携わっています。
また、国立社会保障・人口問題研究所やこども家庭庁の調査・研究グループの一員として、国の政策決定に寄与するデータや研究結果の提供などにも携わっています。
また、国立社会保障・人口問題研究所やこども家庭庁の調査・研究グループの一員として、国の政策決定に寄与するデータや研究結果の提供などにも携わっています。
策定に関わった「さいたま市幼児教育の指針」「戸田市こども計画」
今現在、取り組まれていることは?(研究など)
保育の場における「支援を必要とする家庭で育つ子ども」に対する支援の実態やその在り方について研究をしています。
支援を必要とする子どもや家庭の実態、保育者の支援の様相を調査し、多様な家庭を支えるために必要な専門性について検討しています。
支援を必要とする子どもや家庭の実態、保育者の支援の様相を調査し、多様な家庭を支えるために必要な専門性について検討しています。
これまでの研究に関する著書の一部
子どもが主体的に学ぶためには、安心という基盤が欠かせません。
安心という基盤ができると、主体的に学ぶ姿に繋がり、そしてそれは、最終的に子どもが主体的に生きるための力になります。
よりよい教育にはよりよい生活の支援が欠かせず、そのためには「教育と福祉の連携」が必要であると考えています。
安心という基盤ができると、主体的に学ぶ姿に繋がり、そしてそれは、最終的に子どもが主体的に生きるための力になります。
よりよい教育にはよりよい生活の支援が欠かせず、そのためには「教育と福祉の連携」が必要であると考えています。
その研究に興味を持ったきっかけは?
荒川区子ども家庭支援センター(現・荒川区児童相談所)の相談業務で出会った子どもや家庭との出会いが、多様な子どもや家庭を支える仕組みに関心をもつきっかけとなりました。
荒川区の前に勤務していたお茶の水女子大学附属幼稚園は、日本で最初に設立された伝統ある幼稚園で、幼児教育の偉人と言われる方々も携わってきた日本の一大幼児教育研究の拠点でもあり、とても刺激的かつ学びの多い恵まれた環境でした。
入園には受験が必要な幼稚園なので、教育意識の高い家庭環境で育つ子どもたちの姿がありました。
ただ、自分の育った地域の環境にはない環境で、障がいをもつ子ども、ひとり親家庭、貧困家庭、社会的養護を受ける子ども、外国籍家庭の子どもなどがいないことは、どこかしら不思議な環境だと思っていました。
多様な家庭環境の中で育つ子どもの姿を知り・支えることにも私は関心があるのかもしれない…という気持ちも芽生えてきた時、荒川区子ども家庭支援センターを立ち上げるので来ないか?と声を掛けていただき、勤務することになりました。
荒川区の前に勤務していたお茶の水女子大学附属幼稚園は、日本で最初に設立された伝統ある幼稚園で、幼児教育の偉人と言われる方々も携わってきた日本の一大幼児教育研究の拠点でもあり、とても刺激的かつ学びの多い恵まれた環境でした。
入園には受験が必要な幼稚園なので、教育意識の高い家庭環境で育つ子どもたちの姿がありました。
ただ、自分の育った地域の環境にはない環境で、障がいをもつ子ども、ひとり親家庭、貧困家庭、社会的養護を受ける子ども、外国籍家庭の子どもなどがいないことは、どこかしら不思議な環境だと思っていました。
多様な家庭環境の中で育つ子どもの姿を知り・支えることにも私は関心があるのかもしれない…という気持ちも芽生えてきた時、荒川区子ども家庭支援センターを立ち上げるので来ないか?と声を掛けていただき、勤務することになりました。
現在は児童相談所であることからもお分かりの通り、そこでは多様で過酷な育ちの背景をもつ子どもとの出会いがありました。
保護者が虐待という状況に陥ってしまう環境で育っていたり、そもそも戸籍がなかったり、妊婦健診未受診で生まれてきた子どももいました。
そのような中、ある5歳の子どもと保護者に出会いました。
お母さんは軽度の知的障害をもち、普段の子どもの食事はお菓子やコンビニのおにぎりがメイン、保育所や幼稚園には通っていません。
いわゆる“ネグレクト”という状況です。
いろいろと話を聞いていくと、お母さんには料理を作る習慣がなかったのですね。
当初は、「なんていい加減な…」と率直に感じましたが、家庭の調査を行っていくうちに、お母さん自身もそうした家庭環境で育ち、いじめや差別の経験などから学校とも遠ざかり、そしてひとり10代で親になり、頼れる親族や知人もおらず、孤立した生活を送っていた状況が明らかになってきました。
よく「虐待は連鎖する」といいますが、まさに保護者であるお母さん自身も支援が必要な状態にある中で生き抜いてきたサバイバーであり、もしもお母さん自身が子どもの頃に適切な支援を受けることができていたら、また異なった現実があったのではないかと思います。
保護者が虐待という状況に陥ってしまう環境で育っていたり、そもそも戸籍がなかったり、妊婦健診未受診で生まれてきた子どももいました。
そのような中、ある5歳の子どもと保護者に出会いました。
お母さんは軽度の知的障害をもち、普段の子どもの食事はお菓子やコンビニのおにぎりがメイン、保育所や幼稚園には通っていません。
いわゆる“ネグレクト”という状況です。
いろいろと話を聞いていくと、お母さんには料理を作る習慣がなかったのですね。
当初は、「なんていい加減な…」と率直に感じましたが、家庭の調査を行っていくうちに、お母さん自身もそうした家庭環境で育ち、いじめや差別の経験などから学校とも遠ざかり、そしてひとり10代で親になり、頼れる親族や知人もおらず、孤立した生活を送っていた状況が明らかになってきました。
よく「虐待は連鎖する」といいますが、まさに保護者であるお母さん自身も支援が必要な状態にある中で生き抜いてきたサバイバーであり、もしもお母さん自身が子どもの頃に適切な支援を受けることができていたら、また異なった現実があったのではないかと思います。
かつて勤務していた幼稚園があった文京区と荒川区とは隣の区です。
同じ地域に生きる同じ5歳児でも、こんなにも育つ環境が異なる、この現実にたくさんのことを考えさせられました。
どのような環境に置かれた子どもであっても、全ての子どもによりよく生きる機会が等しく与えられないだろうか・・・
そう考えたときに、自分の原点である幼児教育に大きな意義を見い出しました。
どのような環境に置かれている子どもであっても、園や学校で出会う保育者や教師の存在に力付けられ、学ぶことに力付けられ、教育が子どもの人生の保障のための一つの手段となるのではないかということに意義を見出したことが、自分自身の研究の大きなきっかけとなっています。
同じ地域に生きる同じ5歳児でも、こんなにも育つ環境が異なる、この現実にたくさんのことを考えさせられました。
どのような環境に置かれた子どもであっても、全ての子どもによりよく生きる機会が等しく与えられないだろうか・・・
そう考えたときに、自分の原点である幼児教育に大きな意義を見い出しました。
どのような環境に置かれている子どもであっても、園や学校で出会う保育者や教師の存在に力付けられ、学ぶことに力付けられ、教育が子どもの人生の保障のための一つの手段となるのではないかということに意義を見出したことが、自分自身の研究の大きなきっかけとなっています。
学生時代のことを教えてください
埼玉の自然しかない田舎でのんびり育ちました。
一人で遊んだり、友達や地域の仲間と遊んだりと、遊んでばかりでした。
時代的にも地域的にも幼稚園・小学校・中学校は統制的な雰囲気があったのですが、私は統制されることがあまり好きではなかったので、先生の前では一応それなりにやっている感じを醸し出しつつ、心は自由であろうと決めていました。
大笑いできること、思わず調べたくなることを常に探していたような気がします。
時間を持て余してもいたので、よく老若男女問わず身の回りの人に話かけては、ぼつぼつ話しを聞いていました。
一人で遊んだり、友達や地域の仲間と遊んだりと、遊んでばかりでした。
時代的にも地域的にも幼稚園・小学校・中学校は統制的な雰囲気があったのですが、私は統制されることがあまり好きではなかったので、先生の前では一応それなりにやっている感じを醸し出しつつ、心は自由であろうと決めていました。
大笑いできること、思わず調べたくなることを常に探していたような気がします。
時間を持て余してもいたので、よく老若男女問わず身の回りの人に話かけては、ぼつぼつ話しを聞いていました。
人の語りは最高に面白いです。
話を聞くうちに表面的には見えない、その人の“リアル”が見えてきて、その人の人生の厚みに感心させられることが多くあります。
話を聞いて、互いに話すようになると、次第に仲も深まってくるんですよね。
格好よく言うと、話を聞くことを通した相互行為やラポール形成なるものを、身をもって経験していたのかもしれません。
身の回りの人や状況をよく観察し、身の上話を聞き、描写し、背景や置かれた構造を読み解くことなどに、その頃から関心がありました。
話を聞くうちに表面的には見えない、その人の“リアル”が見えてきて、その人の人生の厚みに感心させられることが多くあります。
話を聞いて、互いに話すようになると、次第に仲も深まってくるんですよね。
格好よく言うと、話を聞くことを通した相互行為やラポール形成なるものを、身をもって経験していたのかもしれません。
身の回りの人や状況をよく観察し、身の上話を聞き、描写し、背景や置かれた構造を読み解くことなどに、その頃から関心がありました。
高校はとにかく自由で面白い女子しかいない空間だったので、関心のあった社会問題なども教室でぼりぼりお菓子を食べながら普通に話せたりしたこともホッとしました。
とにかく関心のあることにはとことん没頭していた、と言えば聞こえはいいですが、好きなことしかしていない幼小中高時代でしたので、当然大学受験は大失敗。
あまり目的も期待もないまま、大学に進学しました。
ただ、偶然出会った友人や先輩、先生方が面白い方々が多く、それは私にとって大きな財産になりました。
当時の進学先は、教員養成というよりも子どもについて教育学・心理学・社会学・社会福祉学・歴史学・児童文化など学際的に研究する視点をもつ環境、今の子ども学部のような雰囲気の学科でした。
そして、それまでの自分の関心が研究課題になったことは大きな転換点になり、自分の関心が「教育学」「社会福祉学」「社会学」の領域にまたがっていることも分かりました。
特に物事の見方・捉え方をより一層身につけたいと思い、大学院在学中には東京大学大学院の社会学の授業やゼミに参加し、一緒に学ばせてもらったりもしていました。
その時のメンバーの方々と、今改めて研究や学会などで再会することもあり、人のつながりの面白さを感じています。
あと、よく国内外に旅に出たり、不自由な環境でキャンプをしたりもしましたね。
初期のフジロックフェスティバルでは、毎年5日間のハードなキャンプを楽しむなど、サバイバルな爆笑旅が好きでした。
とにかく関心のあることにはとことん没頭していた、と言えば聞こえはいいですが、好きなことしかしていない幼小中高時代でしたので、当然大学受験は大失敗。
あまり目的も期待もないまま、大学に進学しました。
ただ、偶然出会った友人や先輩、先生方が面白い方々が多く、それは私にとって大きな財産になりました。
当時の進学先は、教員養成というよりも子どもについて教育学・心理学・社会学・社会福祉学・歴史学・児童文化など学際的に研究する視点をもつ環境、今の子ども学部のような雰囲気の学科でした。
そして、それまでの自分の関心が研究課題になったことは大きな転換点になり、自分の関心が「教育学」「社会福祉学」「社会学」の領域にまたがっていることも分かりました。
特に物事の見方・捉え方をより一層身につけたいと思い、大学院在学中には東京大学大学院の社会学の授業やゼミに参加し、一緒に学ばせてもらったりもしていました。
その時のメンバーの方々と、今改めて研究や学会などで再会することもあり、人のつながりの面白さを感じています。
あと、よく国内外に旅に出たり、不自由な環境でキャンプをしたりもしましたね。
初期のフジロックフェスティバルでは、毎年5日間のハードなキャンプを楽しむなど、サバイバルな爆笑旅が好きでした。
研究や教育外ではどのように過ごしていますか?
子どもの頃と変わらず、一人で遊ぶこと、友達や研究仲間と遊ぶこと、大笑いできること、思わず調べたくなることが生活の基本です。
自分の中で「ボーっとすること」「ワイワイすること」「しんみり語り合うこと」「とことんやること・考えること」の4つのバランスが取れているといい感じです。
ボーっとすることには特に力を入れていて、最近は車の運転をしている時間、街や電車の中の人たち、動物(パンダ・チンパンジーが特に好き)、動物を育てる飼育員さんと動物との関係を見ている時は癒しの時間です。
また、旅に出て、その地場の人の暮らしを観察し、歴史を調べ、身を置き、なり切って過ごしてみることもいいですね(所詮よそ者なんですが)。
地域色が見える「道の駅」も好きなので、ジャンボしいたけを探したりしています。
自分の中で「ボーっとすること」「ワイワイすること」「しんみり語り合うこと」「とことんやること・考えること」の4つのバランスが取れているといい感じです。
ボーっとすることには特に力を入れていて、最近は車の運転をしている時間、街や電車の中の人たち、動物(パンダ・チンパンジーが特に好き)、動物を育てる飼育員さんと動物との関係を見ている時は癒しの時間です。
また、旅に出て、その地場の人の暮らしを観察し、歴史を調べ、身を置き、なり切って過ごしてみることもいいですね(所詮よそ者なんですが)。
地域色が見える「道の駅」も好きなので、ジャンボしいたけを探したりしています。
最近は完全オフの旅はなかなかできませんが、学会参加や研究調査で国内のさまざまな地域に出張する機会が多くあります。
昼はまじめに仕事をして、夜は研究仲間と地場の美味しいお酒と肴をいただきながら、英気を養っています。
大事な仲間がいることは、嘆き合ったり、多くの刺激をもらったり、「こうありたい」を考えるための大きな支えです。
基本的には好きなことしかしてこなかったので、職業に就く際、課せられた仕事ができるのか不安でしたが、一見自分には興味の無い仕事でも、手を付けていくと面白さが見つかってくることが社会人になってからの発見かもしれません。
そして何より、学生さんたちによりよい環境と学びを提供できるようにしたいという責任感が、自分を真面目にさせてくれ、成長させてくれるのだなと感じています。
「自分は社会に出て大丈夫だろうか?」と不安に思う方、大丈夫です。
たくさん遊んで楽しいことを見つける得意さが、仕事での自分を支えてくれます。
昼はまじめに仕事をして、夜は研究仲間と地場の美味しいお酒と肴をいただきながら、英気を養っています。
大事な仲間がいることは、嘆き合ったり、多くの刺激をもらったり、「こうありたい」を考えるための大きな支えです。
基本的には好きなことしかしてこなかったので、職業に就く際、課せられた仕事ができるのか不安でしたが、一見自分には興味の無い仕事でも、手を付けていくと面白さが見つかってくることが社会人になってからの発見かもしれません。
そして何より、学生さんたちによりよい環境と学びを提供できるようにしたいという責任感が、自分を真面目にさせてくれ、成長させてくれるのだなと感じています。
「自分は社会に出て大丈夫だろうか?」と不安に思う方、大丈夫です。
たくさん遊んで楽しいことを見つける得意さが、仕事での自分を支えてくれます。
今後の目標を教えてください
「ハブ(架け橋の役)」になれたら・・・
現場の状況を観察し、話を聞き、共に身を置き、その中で見えてくる課題をトレースし、その課題を構造化し、伝えること(大学での授業、学会発表や論文などで)。
それらを自治体や国の仕事を行う中で、事業や施策、方針などへと繋げていく触媒のように在れたらとは思っています。
そして、いずれその営みが、これからの保育や教育・福祉を担う学生さんたちの力やよりよい子どもの育ちの環境整備へと繋がっていけるよう尽力していきたいと思います。
現場の状況を観察し、話を聞き、共に身を置き、その中で見えてくる課題をトレースし、その課題を構造化し、伝えること(大学での授業、学会発表や論文などで)。
それらを自治体や国の仕事を行う中で、事業や施策、方針などへと繋げていく触媒のように在れたらとは思っています。
そして、いずれその営みが、これからの保育や教育・福祉を担う学生さんたちの力やよりよい子どもの育ちの環境整備へと繋がっていけるよう尽力していきたいと思います。

さいたま市巡回保育相談での一コマ。
園の先生方とカンファレンスを行う中で、課題を見出し、支援の在り方を共に考えています。
記事をご覧の方へメッセージをお願いします

撮影場所:坪井先生の研究室
それぞれの場で出会う人たちに影響を受け、自分なるものが形成されてくるような気がします。
私は明確な目的意識をもった学生生活を送ってはいませんでしたが、その時々に面白い!と関心をもって取り組める思い切りの良さ(フラフラしているとも言える)とそのチャンスをくださった周囲の方々との出会いが、自分を支えてきたようにも思います。
目的意識がある方も、まだふわっとしか見えていない方も、「あ、これは面白いかも」という自分の関心をぜひ大切にしてください。
思い切って飛び込んでみることで、豊かな出会いと経験が待っているはずです。
そうした意味において、東京成徳大学や子ども学部の環境は、あなたの「面白い」を拡げてくれる環境であると思います。
教育の基盤を成している先生方は、広い視野と深い見識をもつ専門性の高い方が揃っています。
私自身も先生方からお話を伺うことが楽しく、優秀な先生方に囲まれて働けることは、恵まれたいい環境だな・・・としみじみ思っています。
私は明確な目的意識をもった学生生活を送ってはいませんでしたが、その時々に面白い!と関心をもって取り組める思い切りの良さ(フラフラしているとも言える)とそのチャンスをくださった周囲の方々との出会いが、自分を支えてきたようにも思います。
目的意識がある方も、まだふわっとしか見えていない方も、「あ、これは面白いかも」という自分の関心をぜひ大切にしてください。
思い切って飛び込んでみることで、豊かな出会いと経験が待っているはずです。
そうした意味において、東京成徳大学や子ども学部の環境は、あなたの「面白い」を拡げてくれる環境であると思います。
教育の基盤を成している先生方は、広い視野と深い見識をもつ専門性の高い方が揃っています。
私自身も先生方からお話を伺うことが楽しく、優秀な先生方に囲まれて働けることは、恵まれたいい環境だな・・・としみじみ思っています。
そして大学の主役である学生さんたち。
リアルな現場の話を面白がってくれたり、目的を持ったらとことん取り組めるひたむきな姿があります。
そして、4年間でこんなにも変われるのだと驚きの成長を毎年見せてくれています。
着実さが頼もしさをつくり出し、真剣に取り組むことが「かっこいい」と互いを認め合える風土が東京成徳にはある気がします。
卒業してしまうのが寂しく、一緒に働いたらさぞかし頼もしいだろうなと思っています。
卒業後は、保育士や幼稚園教諭、小学校教諭はもちろん、児童相談所や児童発達支援センター、子ども関連の一般企業、子どもとは直接的な関わりがない仕事に就く卒業生もいますが、大学で広く「人」を学んできている経験が、それぞれの場での活躍や必要とされる人材を生み出していると言えます。
「子どもにとってよりよいこと」とは何か、私には何ができるだろうか、そしてどのような社会のあり方が考えられるのだろうか・・・
東京成徳のこの環境で、自分だけの「面白い」を見つけ、探究してみてください。
リアルな現場の話を面白がってくれたり、目的を持ったらとことん取り組めるひたむきな姿があります。
そして、4年間でこんなにも変われるのだと驚きの成長を毎年見せてくれています。
着実さが頼もしさをつくり出し、真剣に取り組むことが「かっこいい」と互いを認め合える風土が東京成徳にはある気がします。
卒業してしまうのが寂しく、一緒に働いたらさぞかし頼もしいだろうなと思っています。
卒業後は、保育士や幼稚園教諭、小学校教諭はもちろん、児童相談所や児童発達支援センター、子ども関連の一般企業、子どもとは直接的な関わりがない仕事に就く卒業生もいますが、大学で広く「人」を学んできている経験が、それぞれの場での活躍や必要とされる人材を生み出していると言えます。
「子どもにとってよりよいこと」とは何か、私には何ができるだろうか、そしてどのような社会のあり方が考えられるのだろうか・・・
東京成徳のこの環境で、自分だけの「面白い」を見つけ、探究してみてください。
皆さま、いかがでしたか?
記事をご覧になって、東京成徳の研究やその研究者である先生のことについて、理解ができたり、少しでも身近に感じたりしていただけたら、うれしいです。
また、もしこの記事を読んで、先生の研究や先生、大学のことに興味を持った高校生や受験生がいらっしゃったら、ぜひオープンキャンパスや学校見学にお越しください。
皆さまのご来校をお待ちしています。
記事をご覧になって、東京成徳の研究やその研究者である先生のことについて、理解ができたり、少しでも身近に感じたりしていただけたら、うれしいです。
また、もしこの記事を読んで、先生の研究や先生、大学のことに興味を持った高校生や受験生がいらっしゃったら、ぜひオープンキャンパスや学校見学にお越しください。
皆さまのご来校をお待ちしています。
【制作・企画】
学校法人東京成徳学園
法人本部 企画調査室
TOKYO SEITOKU NOW制作担当
学校法人東京成徳学園
法人本部 企画調査室
TOKYO SEITOKU NOW制作担当