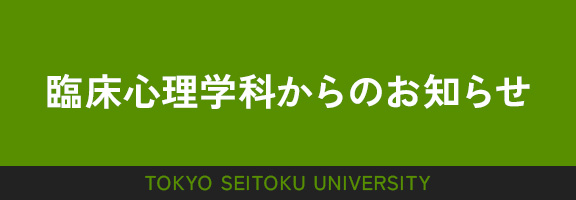研究紀要
東京成徳大学研究紀要-応用心理学部・大学院心理学研究科-
本サイトは、『東京成徳大学 心理学研究』等の目次、抄録、全文を公開するものです。
本サイトの利用は、調査・研究・教育または学習を目的とする場合に限ります。営利目的での利用は禁じます。
サイト内で閲覧できる論文は印刷媒体と同様に著作権法によって保護されます。論文を利用する場合は、著作権法の規定を遵守して下さい。
本サイトの利用は、調査・研究・教育または学習を目的とする場合に限ります。営利目的での利用は禁じます。
サイト内で閲覧できる論文は印刷媒体と同様に著作権法によって保護されます。論文を利用する場合は、著作権法の規定を遵守して下さい。
東京成徳大学 心理学研究
2022年度、『東京成徳大学研究紀要-人文学部・国際学部・応用心理学部-』、心理学研究科が発刊していた『東京成徳大学臨床心理学研究』が廃刊になり、2024年度より応用心理学部・心理学研究科が合同で『東京成徳大学 心理学研究』第1号を刊行いたしました。応用心理学部臨床心理学科・健康スポーツ心理学科・大学院心理学研究科の専任教員および共同研究者による心理学研究に関する論文を掲載しています。
心理学研究 第2号
出版年:令和7年(2025年)3月
| タイトル | タイトル |
|---|---|
| 執筆規定 | |
| 競技者によって知覚されたコーチの変革型リーダーシップ行動が中高生男性バスケットボール競技者の心理と行動へおよぼす影響:コーチとの人間関係,プレーへの動機づけ,社会化への影響 | 夏原 隆之 川北 準人 市村 操一 雨宮 怜 |
| 蛙化現象の「元祖」と「もどき」を弁別する―概念の流行に伴う定義と用例の広まりに応じた検討の試み― | 伊藤 真弥 関谷 大輝 |
| デジタルな授業を,アナログで描く。―大学のオンライン授業でグラフィックレコーディングを活用する実践研究― | 岡崎 桃子 関谷 大輝 |
| 男性同性愛者のマイノリティ・ストレスが精神的健康に及ぼす影響―本来感と孤独感を媒介として― | 大野 功仁郎 吉田 富二雄 |
| 感覚処理感受性の高い人におけるぬいぐるみを抱くことのリラクセーション効果 | 齋藤 桃 板生 研一 塚田 知香 |
| コンパッションの介入効果を妨げる要因に関する研究―呼吸法,マインドフルネス,精神的疲労の視点から― | 石村 郁夫 相馬 遥香 |
| 高齢者の“よく生きること(better-being)”―日本舞踊教室における後期高齢女性の会話を通じた関係性と実践のひろがり― | 内藤 孝一 茂呂 雄二 |
| 強みに焦点を当てた療育プログラムの必要性に関する研究―保護者の療育への期待と育児ストレスの視点から― | 隅井 樹 石村 郁夫 |
| 養育者の養育態度と大学生の労働価値観の関係―養育者の労働価値観を媒介変数として― | 米澤 昌乃 阿部 宏徳 |
| 境遇活用スキルの向上に焦点を当てたキャリア教育プログラムの試行と効果検証― 境遇活用スキルと職業未決定に着目して― | 赤城 知里 西村 昭徳 井上 忠典 |
| 大学生が社交不安を感じる状況把握のための基礎的研究 | 根津 克己 |
| スポーツコーチのリーダーシップの研究の近年の動向 | 川北 準人 石村 郁夫 遠香 周平 雨宮 怜 市村 操一 |
| 編集規定 |
心理学研究 第1号
出版年:令和6年(2024年)3月
| タイトル | 執筆者 |
|---|---|
| 執筆規定 | |
| 「東京成徳大学 心理学研究」創刊にあたって | 一谷 幸男 出雲 輝彦 石隈 利紀 |
| 個人の資源としての心理的ウェルビーイング-JD-Rモデルにおける幸福感の位置づけ- | 八塚 智子 塚田 知香 |
| 小中学生用教師評定日本語版マクロスキー実行機能尺度(J-MEFS)の作成 | 名越 斉子 山口 一大 飯利 知恵子 石隈 利紀 |
| 思いやり反応尺度の作成と信頼性・妥当性の検証-コンパッションへの恐れを和らげるモデルの提案- | 石村 郁夫 中谷 隆子 葉山 大地 佐藤 修哉 大矢 薫 川﨑 直樹 |
| 結婚の自己決定意欲が将来への時間的展望に及ぼす影響-結婚への動機づけおよび伝統的結婚観に着目して- | 千速 拓真 江口 めぐみ |
| 大学生の強迫傾向が共感性を通じて対人関係様式に与える影響 | 波多野 智弘 石村 郁夫 |
| HSPの情動伝染が精神的健康に及ぼす影響 | 森 早也佳 塚田 知香 |
| フィードバックを伴う問題解決過程におけるプランニングと創造性-言語的指標を中心とした分析による検討- | 別府さおり 石原 章子 奥畑 志帆 井上 知洋 大柳 俊夫 岡崎 慎治 |
| 社交不安がセルフ・コンパッションを介して社交場面で生じる恥対処に及ぼす影響 | 星 裕人 石村 郁夫 |
| 同調行動が青年の適応感に与える影響-規範的影響,情報的影響,FoMOの観点から- | 土屋 紫音 田中 速 |
| スポーツにおけるセルフ・コンパッション研究の動向 | 本多 麻子 石村 郁夫 雨宮 玲 荒木 雅信 市村 操一 |
| 編集規定 |
東京成徳大学研究紀要-人文学部・国際学部・応用心理学部-
2019年に国際学部が発足し、2019年から2022年に発行された研究紀要第27号から第29号については、3学部合同で刊行しました。
第29号
出版年:令和4年(2022年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
|---|---|
| ラオスの農村部における貧困削減と農業・農村開発:JICAの農村開発プロジェクトから得られた示唆 | 芳賀 克彦 |
| 思いやりの表出と抑制―相手を傷つけないために思いやり行動を抑制する― | 本多 麻子 |
| A Study on W. B. Yeats’s Love Poems (1)-With Particular Reference to His Early and Middle Poems- | 江澤 恭子 |
| ハリスと東海道(10) ―ヒュースケン日記とともに― | 山下 琢巳 |
| 最適化問題における進化的計算アルゴリズムの比較 | 岩瀬 弘和 |
| 柔道競技者の怒りの研究:練習と試合での怒りの強度と対処法とそれらの効果 | 岡田 弘隆 廣川 充志 久保田 浩史 小野 卓志 市村 操一 |
| 横光利一の『碑文』論 ―聖書との関わりを中心に― | 崔 英姫 |
| 日本におけるイカロス表象 ―「失墜」から「昇天」へ | 小橋 玲治 |
第28号
出版年:令和3年(2021年)3月15日
第27号
出版年:令和2年(2020年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
|---|---|
| 明治期における日本語の言語適応再考(1) | 今仲 昌宏 |
| 国際政治における韓国「新軍部」台頭に関する考察 | 李 正勲 |
| PBL授業の前後におけるキャリア意識の変化-社会人基礎力「チームで働く力」の自己評価の変化- | 猪又 優 |
| 生活に困窮する求職者の特徴-就労支援プラン作成者の事例から- | 朝比奈 朋子 杉野 緑 |
| 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」に関する考察 | 江間 由紀夫 |
| スポーツ・コーチ教育への変革型リーダーシップ理論の導入の試みの紹介 | 夏原 隆之 中山 雅雄 岡田 弘隆 川北 準人 市村 操一 |
| 達成と情熱のポジティブ心理学的検討-Grit,レジリエンス, 楽観性の関連- | 本多 麻子 |
| バスケットボールを始めたきっかけが目標志向性に与える影響 | 山田 裕生 |
| 安井てつのウェールズ体験 | 小橋 玲治 |
| ハリスと東海道(8)-ヒュースケン日記とともに- | 山下 琢巳 |
| A Discussion on the New Zealand Short Story (2) | 江澤 恭子 |
| 国連のGNI比0.7%のODA目標と今後の展望 | 芳賀 克彦 |
| 横光文学と聖書-「新感覚派」時代の短編作品に着目して- | 崔 英姫 |
東京成徳大学研究紀要-人文学部・応用心理学部-
本学人文学部は、2008年に心理系2学科を分離独立させ、人文学部と応用心理学部の2学部体制をとることとなりましたが、研究紀要については、従来の編集方針を踏まえ2学部合同で刊行することとしました。これに伴い、本研究紀要の性格を明確にするため、第16号からは紀要の名称を上記のように変更しました。
第26号
出版年:平成31年(2019年)3月15日
第25号
出版年:平成30年(2018年)3月15日
第24号
出版年:平成29年(2017年)3月15日
第23号
出版年:平成28年(2016年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 時間枠制約付き配送計画問題に対するヒューリスティック解法 | 岩瀬弘和 |
| 我が国における「気になる子ども」の支援に関する一考察-北欧の支援システムを通して- | 石田祥代 野澤純子 藤後悦子 |
| ピアスタッフとソーシャルワーカーの関係性に関する一考察 | 江間由紀夫 |
| 公開シンポジウム「手をとり合おう!教育と福祉-共生社会の実現を、教育と福祉から考える-」報告 | 別府さおり 宮山篤 鈴木翠 白波瀬正人 前川久男 |
| 自閉症スペクトラムの児童・青年における罪悪感と恥について | 菊池春樹 |
| 声の高さが話者の性格および有能さの評価に与える影響 | 石井辰典 |
| 学校運動部のコーチが感じているコーチと競技者の人間関係 | 川北準人 山口香 中瀬雄三 村田洋佑 市村操一 |
| 高校サッカー競技者とコーチとの人間関係についての検討 | 木幡日出男 岡田弘隆 石井辰典 夏原隆之 市村操一 |
| 大学生の日常的なポジティブイベントの構成要素-大学生はSNSよりも直接的なコミュニケーションに幸せを感じる- | 本多麻子 |
| ハリスと東海道(4)-ヒュースケン日記とともに- | 山下琢巳 |
| 英語音声指導における中和について | 今仲昌弘 |
| Colours as Represented in Tess of the D'Urbervilles (2) | 江澤恭子 |
| わが国の観光推進組織に関する一考察 | 井上博文 |
| 中止された1908年ロンドン・オリンピックのゴルフ | 市村操一 |
| 社会科教育法における世界遺産の教材化と模擬授業の実践 | 小松伸之 |
| 公債市場補完制度に関する一般理論 | 中村宙正 |
| 反道徳的ステレオタイプを抑制する道徳教育-道徳授業におけるメタ認知的知識習得の有用性- | 鑓水浩 |
| 『チャーリーとの旅-アメリカを求めて』にみる「迷子」の表象 | 林惠子 |
| 谷崎潤一郎の出立期を問う-『幇間』における「暗示」- | 西元康雅 |
| 東京成徳大学日本伝統文化学科蔵 木呂子斗鬼次「林原耕三宛書簡」翻刻 | 庄司達也 |
| 東京成徳大学人文学部・応用心理学部研究プロジェクト課題(2015年度) |
第22号
出版年:平成27年(2015年)3月15日
第21号
出版年:平成26年(2014年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 英語発音習得における成人学習者の抑制要因 | 今仲昌宏 |
| 達成感を味わってもらうことによって学生の学ぶ意欲を引き出す試み | 周建中 |
| IRELAND – A Chronology | 江澤恭子 |
| ロールシャッハ・テスト用データベースアプリケーションの作成 | 阿部宏徳 |
| 性問題行動を示す自閉症スペクトラム障害の青年のためのコーピング・スキル・トレーニング・プログラム開発の試み | 菊池春樹 森田展彰 武井仁 田上洋子 |
| 「生活支援論」再考−谷中輝雄の遺したもの | 江間由紀夫 |
| 箱庭の手続きを構造化することの効果について―主観的自己評価と心拍変動による検討― | 加地雄一 関谷大輝 鎌田弥生 |
| 構造化箱庭の特徴および有効性―自由記述データのテキストマイニングによる検討― | 関谷大輝 加地雄一 鎌田弥生 |
| 風景構成法における距離感と構成型との関係に関する考察 | 鎌田弥生 加地雄一 関谷大輝 |
| 単身低所得高齢者の支援のあり方に関する一考察 | 渡辺央 |
| ハリスと東海道(2)―ヒュースケン日記とともに― | 山下琢巳 |
| 現代金融論の課題(上) | 長谷部孝司 |
| 納期の異なるフローショップ・スケジューリング問題への遺伝的局所探索法の適用 | 岩瀬弘和 |
| 青年のスポーツにおける価値観、達成動機、社会的態度の関係の再検討 | 浦井孝夫 望月幹夫 川北準人 市村操一 |
| バドミントンのサービスにおける心理・生理・行動指標の関連 | 本多麻子 |
| マインドリーディングの推測方略―感情,選好,性格の推測における投影とステレオタイプ化の使い分け― | 石井辰典 |
| 東京成徳大学人文学部・応用心理学部研究プロジェクト課題(2013年度) |
第20号
出版年:平成25年(2013年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| バスケットボール選手の価値観と達成指向はスポーツ態度を予測するか? | 市村操一 川北準人 石村郁夫 浦井孝夫 羽鳥健司 近藤明彦 |
| 高等学校男子バスケットボール競技者の積極的関与とバーンアウトの関係 | 石村郁夫 川北準人 浅野健一 羽鳥健司 長岡修二 市村操一 |
| 大学男子バスケットボールの競技力向上に関する一考察―関東大学バスケットボール連盟における東京成徳大学の活動を事例に― | 川北準人 |
| ある中国帰国者三世のひとりだち―リフレクシヴ・エスノグラフィによる発達文化研究の試み― | 神谷純子 |
| ハリスと東海道(1)―ヒュースケン日記とともに― | 山下琢巳 |
| フローショップスケジューリング問題における発見的探索アルゴリズムの比較 | 岩瀬弘和 |
| 英語/l/の母音化と音声指導上の問題について | 今仲昌宏 |
| ホスピタリティ産業(ホテル業)におけるグループの行動と業績の一考察 | 井上博文 |
| 構造化箱庭療法の有効性に関する検討―事例分析を通して― | 加地雄一 松浦隆信 鎌田弥生 |
| 構造化箱庭療法の有効性に関する検討―量的データの分析から― | 松浦隆信 加地雄一 鎌田弥生 |
| 構造化箱庭療法の有効性に関する検討―修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いての質的データの分析から― | 鎌田弥生 加地雄一 松浦隆信 |
| 小・中学校における特別支援教育コーディネーターのコーディネーション行動 | 中村真理 長谷部慶章 阿部博子 |
| 相談援助実習の実習前評価についての実態 | 渡辺央 |
| 東京成徳大学人文学部・応用心理学部研究プロジェクト課題(2012年度) |
第19号
出版年:平成24年(2012年)3月15日
第18号
出版年:平成23年(2011年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 日本語入力練習システムの開発とその効果 | 岩瀬弘和 |
| 1990 年代半ば以降の日本の金融改革(中) ―産業構造の転換の遅れと金融システムの転換の遅れ― | 長谷部孝司 |
| わが国の観光案内所のサポート組織の概要と行政の役割 ―千葉県を事例として― | 井上博文 |
| 成年後見人の職務 | 山口春子 |
| 日本の大学における聴覚障害者支援活動 ―ある小規模校の報告― | 應武マーガレットパイン 中山哲志 |
| 韓国ソウル大学路における文化地区指定とソウルストリートアーティスト事業 | 水谷清佳 |
| 英語音韻論における語彙レベルの心理的実在 | 今仲昌宏 |
| 日中両言語におけるダイクシス指示表現の比較対照 ―認知言語学的な観点による一考察― | 単 娜 |
| 前田斉広夫人真龍院の漢詩 | 直井文子 |
| 埼玉県秩父市贄川猪狩神社の狼信仰に関する一考察 | 西村敏也 |
| 東京成徳大学人文学部・応用心理学部研究プロジェクト課題(2010年度) |
第17号
出版年:平成22年(2010年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 声楽のための英語発音法に関する分析(3) | 今仲昌宏 |
| 近年英語に取り入れられた日本語語源語彙に対する北米英語話者の理解とその文法的使用 | 應武マーガレットパイン |
| 項目反応理論による新入生のコンピュータ・リテラシーの測定 | 川合治男 福山裕宣 岩瀬弘和 半田勝久 |
| 1990 年代半ば以降の日本の金融改革(上) ―産業構造の転換の遅れと金融システムの転換の遅れ― | 長谷部孝司 |
| ジョブの納期の異なるフローショップスケジューリング問題 | 岩瀬弘和 |
| 社会福祉施設職員の職務ストレッサーに関する基礎的研究 | 鎌田大輔 |
| 事例の関連度が説明文の読解過程に与える効果 | 海保博之 藤岡真也 |
| スポーツにおけるポジティヴな社会的態度の決定要因としての価値観と達成目標 | 川北準人 羽鳥健司 近藤明彦 市村操一 |
| リゾート法と地域社会 | 岡田一郎 |
| 会話における語気助詞“?”のコミュニケーション上の機能 | 楊 虹 |
| 賴杏坪の詩 | 直井文子 |
| 書評 散歩の文化史(2) | 市村操一 近藤明彦 |
| 東京成徳大学人文学部・応用心理学部研究プロジェクトの課題(2009年度) |
第16号
出版年:平成21年(2009年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| チームワークづくりのためのメンタルトレーニング -グループエンカウンターのチームづくりへの応用- | 川北準人 市村操一 國分康孝 |
| 声楽のための英語発音法に関する分析(2) | 今仲昌宏 |
| 日本への外国人旅行客がリピーターになる理由に関する調査報告 | 玉川惠子 |
| 「マダン」研究史のための予備的考察 | 水谷清佳 |
| 東京成徳大学における新入生のコンピュータ・リテラシーに関する調査 | 川合治男 福山裕宣 岩瀬弘和 半田勝久 |
| 信頼性理論を用いた生産ラインシステムにおける デバッギング作業に関する研究 | 岩瀬弘和 |
| 1980年代日本の金融自由化の論理 -産業構造の転換の遅れと金融改革の遅れ- | 長谷部孝司 |
| 会話における語気助詞 “?” の機能に関する一考察 | 楊虹 |
| 賴春水の詩 | 直井文子 |
| 書評 散歩の文化史 | 市村操一 近藤明彦 |
| 東京成徳大学人文学部・応用心理学部研究プロジェクト課題(2008年度) |
東京成徳大学研究紀要-人文学部-
本学は、1993 年に人文学部として開学しましたが、2004 年に子ども学部を増設しました。これに伴い、本研究紀要の性格を明確にするため、第14 号からは紀要の名称を上記のように変更しました。
第15号
出版年:平成20年(2008年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| パラメータフリー遺伝的アルゴリズムによる最短ネットワーク問題の解法 | 岩瀬弘和 |
| 境界線におけるW.B.イェイツ ―“The Lake Isle of Innisfree”分析― | 栗原晶江 |
| 声楽のための英語発音法に関する分析(1) | 今仲昌宏 |
| スペイン内戦期のユーゴスラヴィア共産党―チトー指導部確立との関連で― | 岡本 和彦 |
| リレーションを重視したオリエンテーションが新入生の大学生活適応感に及ぼす影響 | 西村昭徳 石崎一記 |
| 成年後見制度 ―「自己決定の尊重」と「保護」の理念の調和― | 山口春子 |
| 地域福祉における行政機関と高等教育機関の協働事業に関する実践研究 | 石田祥代 伊藤栄治 今中博章 鎌田大輔 西村昭徳 根津克己 羽鳥健司 半田勝久 |
| Gairaigo ― Remodelling Language to Fit Japanese | 應武マーガレットパイン |
| 国立公園のインディアン―世紀転換期の自然をめぐる言説と観光産業― | 杉本裕代 |
| 拮抗する「伝統」―金泰午と白秋の童謡論を中心に― | 黄善英 |
| 中日接触場面の初対面会話における「ね」の分析 | 楊虹 |
| ―共感構築の観点から―齋藤拙堂と「狂」 | 直井文子 |
| 書評 日山紀彦『「抽象的人間労働論」の哲学』を読む | 田中史郎 |
| 東京成徳大学人文学部研究プロジェクト課題(2007年度) |
第14号
出版年:平成19年(2007年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 分数の概念獲得の過程 | 小林厚子 |
| 異なる体育プログラムが精神的健康におよぼす影響の比較研究 | 出雲輝彦 唐沢洋子 市村操一 |
| 障害者自立支援法における障害福祉サービス支給決定基準 | 山口春子 |
| わが国の学生相談に対する援助要請研究の動向と課題 | 木村真人 |
| 概念メタファーによるイディオムの学習 | 今仲昌宏 |
| 千葉県の観光に関する一考察 -外国人観光客受け入れの観点から- | 玉川惠子 |
| 『サイバースペース独立宣言』10周年+α -アメリカ起源のネット文化とその行方- | 高野 泰 |
| 芥川龍之介と養父道章 -所謂「自伝的作品」の読解のために(一)- | 庄司達也 |
| 近代における能の囃子方 | 奥山けい子 |
| 東京成徳大学人文学部研究プロジェクト課題(2006年度) |
第13号
出版年:平成18年(2006年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 韓国人留学生文学青年たちの日本近代詩理解および西欧詩との接触 | 金恩典 |
| 英語表現における換喩と婉曲表現について | 今仲昌宏 |
| わが国の篤志病院 | 長畑正道 |
| 被保護者の「自立助長」と高校就学費 | 山口春子 |
| 発達障害児の教育実践におけるカリキュラム依拠 ダイナミック・アセスメントの可能性と課題 | 今中博章 |
| 大学生の学生相談への被援助志向性と 援助サービスの形態との関連 | 木村 真人 |
| 芥川龍之介の聴講ノート「欧州最近文芸史 大塚教授 VOL.Ⅰ」翻刻(承前) | 庄司達也 野呂芳信 |
| 間狂言の自由性 -黒川能における展開- | 奥山けい子 |
| 東京成徳大学研究プロジェクト課題(2005年度) |
第12号
出版年:平成17年(2005年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 私の医学教育・医療改革論 | 長畑正道 |
| 学生相談機関の名称と被援助志向性との関連について | 木村真人 |
| W.Hazlittの文章道―感性表現の道― | 中川誠 |
| 英語名義論における有契性と換喩的表現について | 今仲昌宏 |
| 芥川龍之介の聴講ノート「欧州最近文芸史 大塚教授 VOL.I」 | 庄司達也 野呂芳信 |
| 抽象的人間労働の研究(7)―〈抽象的人間労働〉概念規定をめぐる係争史― | 日山紀彦 |
| 韓国高麗時代の石造弥勒像の特色に関する一試論―灌燭寺の石造菩薩立像を中心に― | 金丸和子 |
| 東京成徳大学研究プロジェクト課題(2004年度) | |
| 総目次 |
第11号
出版年:平成16年(2004年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 英語音声指導における音声表記(2) | 今仲昌宏 |
| Montaigne and Hazlitt:Pioneers of the English Romantics | 中川誠 |
| 未堂 徐廷柱の「新婦」の解明 | 金恩典 |
| 日本語を母語とする韓国語学習者による韓国語の平音・濃音・激音の発音と聴き取り:聴き取り調査の結果をもとに | 古閑恭子 |
| 論理療法のABC理論による対人不安の検討 | 木村真人 |
| 義務教育段階における福祉教育 | 中山哲志 宮本文雄 今中博章 |
| 私の教育改革論:「独立自尊」と「自由」の精神を基礎にして | 長畑正道 |
| 「散歩」という言葉のはじまりと明治時代の散歩者たち | 市村操一 近藤明彦 |
| 中川孝筆記「芥川龍之介『ポオの一面(講演)』」及び新潟高等学校講演会関連資料の翻刻:「芥川龍之介の講演旅行」補遺(三) | 庄司達也 |
| 岩手県東山町松川所在の二十五菩薩像の現状と問題点 | 金丸和子 |
| 明治後期の黒川狂言:東京公演をめぐって | 奥山けい子 |
| 抽象的人間労働の研究<6>:<具体的有用労働時間>による<抽象的人間労働時間>の計量の構図 | 日山紀彦 |
| 真の生きる力を育てる教育の在り方についての基礎研究 :実践現場に学ぶ教育活動の創造 | 富田初代 |
| 東京成徳大学研究プロジェクト課題(2003年度) |
第10号
出版年:平成15年(2003年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 幼児期における身体内イメージの発達(2) | 井桁重乃 |
| 聴覚障害児における算数の学力 | 中村真理 |
| デンマークにおける断種法制定過程に関する研究 | 石田祥代 |
| 愛着理論と精神保健:臨床場面における内的作業モデルの適用 | 藤本昌樹 |
| 英語音声指導における音声表記(1) | 今仲昌宏 |
| ジーン・リースにおけるアイデンティティーの回復:‘Let Them Call It Jazz’における「庭」と「歌」 | 栗原晶江 |
| 共和主義の精神、共和国の身体:ベンジャミン・ラッシュの「医学のアメリカン・システム」 | 高野泰 |
| 相貌端厳な仏像と宝冠弥勒の美 | 金丸和子 |
| 頌声考 | 青栁隆志 |
| 「千人切」考 | 奥山けい子 |
| 芥川龍之介原作、三島由紀夫脚色「地獄変」の「改訂上演本」:大阪歌舞伎座再演用上演台本における川尻清潭の補綴 | 庄司達也 |
| 抽象的人間労働の研究<5>:<抽象的人間労働>の社会関係反照規定性 | 日山紀彦 |
| 長期化する不良債権問題と金融構造改革の遅れ | 長谷部孝司 |
| 東京成徳大学研究プロジェクト課題(2002年度) |
第9号
出版年:平成14年(2002年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 広東海陸豊地域の民俗宗教 | 志賀市子 |
| 賢治と悟空、そして「尊馬油」と「辣油」 | 王敏 |
| 連結発話の原理と指導 | 今仲昌宏 |
| A Comparative Study of 'The Ultimate Love' in Paradise Lost and Shitsurakuen | 野呂有子 |
| ウォータールー・スタンフォード集団催眠感受性尺度:形式C(WSGC)短縮版の作成と検討 | 徳田英次 |
| 抽象的人間労働の研究(4) | 日山紀彦 |
| 福祉国家体制の動揺と金融構造改革の課題 | 長谷部孝司 |
| 東京成徳大学研究プロジェクト課題(2001年度) |
第8号
出版年:平成13年(2001年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 施設利用高齢者の心理的援助に関する研究:回想法によるコミュニケーションの改善に向けて | 渡邉映子 宮本文雄 森俊之 |
| 学習領域自己概念の性差に関する研究 | 佐藤純 |
| 嫌悪場面における近交系マウスの行動:Defensive Burying実験場面での検討 | 森俊之 |
| 's'属格と'of'属格 | 海老名洸子 |
| 異文化交流のひとこま:ヴェルハーレンと縮緬本 | 村松定史 |
| 英語学習と行動規範についての一考察 | 今仲昌宏 |
| ベンジャミン・ラッシュと精神医学の誕生 | 高野泰 |
| ヴァチカン図書館蔵『葡日辞書』所収日本語の語彙的特徴 | 斎藤博 |
| 宮沢賢治における「聖人」のモデル(2) | 王敏 |
| 香港・広東地域の宗教文化に関する邦文文献:回顧と展望 | 志賀市子 |
| アカン語調査初期報告 | 古閑恭子 |
| 高齢者のイメージ(1):KJ法による高齢者イメージの分類 | 仲本美央 藤本昌樹 |
| 子どもの社会適応に関する家族の影響:共分散構造分析によるモデルの検討 | 藤本昌樹 |
| 高原夏期大学の芥川龍之介:資料 小尾二三香「芥川先生を迎えて」翻刻 | 庄司達也 |
| 滝沢家の食事表現:嘉永元年及び安政五年の日記から | 大久保恵子 |
| 東京成徳大学研究プロジェクト課題(2000年度) |
第7号
出版年:平成12年(2000年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 対訳辞書索引の翻字について:『自筆西日辞書』の索引などをめぐって | 斎藤博 |
| 宮沢賢治における「聖人」のモデル(1) | 王敏 |
| 日本人との会話における外国人留学生の意識的配慮の検討 | 一二三朋子 |
| 英語倒置構文の動詞 | 海老名洸子 |
| 日本人学習者の英語発音モデル | 今仲昌宏 |
| 意識における「風景」:「ピクチャレスク」とは何か? | 栗原晶江 |
| 犯罪、身体、刑罰:共和主義者の刑罰改革 | 高野泰 |
| 福祉心理学科学生の福祉意識に関する調査研究 | 渡邉映子 宮本文雄 |
| 聴覚障害児の文章読解力(3):リーディングスパンとの関係 | 中村真理 |
| 介護保険:保険事故の範囲と給付の限界 | 山口春子 |
| 同質グループを対象として専門職養成を行う場合のグループ・ワークについての研究:グループワーカーの介入のあり方について | 益満孝一 西原尚之 |
| 児童虐待防止に関する情報伝達の在り方について(1):絵本を利用した情報伝達 | 仲本 美央 |
| 多言語社会ガーナの言語事情 | 古閑恭子 |
| ミダース王をめぐる音楽=神話学的雑考 | 西澤龍生 |
| 構造改革を迫られる金融システム | 長谷部孝司 |
| 『路女日記』錯簡考 | 大久保恵子 |
| 東京成徳大学研究プロジェクト課題(1999年度) |
第6号
出版年:平成11年(1999年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| モンテーニュ再考:ルネサンス人の生と死 | 中川誠 |
| フォークナーの『アブサロム、アブサロム!』におけるイタリック体の使用について | 前田洋文 |
| 日本人学習者の英語イントネーションの類型 | 前田洋文 今仲昌宏 |
| 英語倒置構文の機能的一考察 | 海老名洸子 |
| 『リチャード三世』における超自然 | 髙山浩子 |
| 宮沢賢治研究の50年:中国への紹介 | 王敏 |
| ミカヅキサマを祀る習俗:栃木県河内郡南河内町を中心に | 松崎かおり |
| 高齢精神遅滞者の福祉処遇に関する研究〔第4報〕:施設利用者の疾病と死亡について | 渡邉映子 宮本文雄 今井秀雄 今村理一 小沼肇 渡辺隆 |
| 内観療法の若干の理論的考察とその実際:福祉心理学の立場より | 岡田明 |
| 確率判断の認知心理(2) | 小林厚子 |
| The Influence of Motivation on Self-Regulated Learning in School Subjects | 谷島弘仁 |
| 大学生・看護学生に対する構成的グループ・エンカウンターの効果とその効果を予測する要因について | 斎藤義浩 |
| 運動課題遂行中の自発的発話の様相 | 藤岡久美子 |
| ブラック・アフリカと文学:リベリアのヴァイ文字を例に | 古閑恭子 |
| 『影の帝冠』をめぐって:R・ウシグリと反歴史 | 西澤龍生 |
| 日本的経営とME化 | 長谷部孝司 |
| 菊池寛「久米正雄宛書簡」翻刻・注釈 :第四次「新思潮」出発期についての考察のために | 庄司達也 |
| 東京成徳大学研究プロジェクト課題(1998年度) |
第5号
出版年:平成10年(1998年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 文人政治家の悲劇と栄光:Edmund Burke | 中川誠 |
| スティービー・スミスの詩の評価と人気 | 金沢融 |
| 異文化としての英語学習と母語環境 | 今仲昌宏 |
| 中国「花」文化:桂花考 | 王敏 |
| 第1次世界大戦後のラトヴィヤ外交政策の意味:地域協力の視点から | 志摩園子 |
| 高齢精神遅滞者の福祉処遇に関する研究[第1報]:施設利用者についての基礎調査 | 渡邉映子 宮本文雄 今井秀雄 今村理一 小沼肇 |
| 確率判断の認知心理(1) | 小林厚子 |
| 介護保険制度の仕組みと構造 | 山口春子 |
| 聴覚障害児の文章読解力(2) | 中村真理 |
| 集団援助技術の基本的技術:観察技術と記録技術を中心に | 益満孝一 |
| クラスの動機づけ構造を規定する要因に関する検討 | 谷島弘仁 |
| バスケットボールにおける集団戦術に関する一考察 | 川北準人 |
| 歌うこと、舞うこと、語ること:ワルター・F・オットーにおけるギリシア神観と人間の形姿 | 西澤龍生 |
| 購買手段としての貨幣と価値尺度論 | 長谷部孝司 |
| 「游心帳」翻刻:小穴隆一旧蔵資料紹介 | 庄司達也 |
| 朝鮮における道仏二教と巫俗の交渉:附、朝鮮本『仏説広本太歳経』影印 | 増尾伸一郎 |
| 東京成徳大学研究プロジェクト課題(1997年度) |
第4号
出版年:平成9年(1997年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| モラリストのShakespeare批評:JohnsonとHazlitt | 中川誠 |
| スティービー・スミスの『国境を越えて』を読む | 金沢融 |
| 談話に先行詞を持たない代名詞 | 海老名洸子 |
| 英語教育と文化相対主義 | 今仲昌宏 |
| WALLACE STEVENSにおける抽象概念の表出:”Anecdote of the Jar”の分析 | 栗原晶江 |
| Structure de Bruges-la-Morte | 村松定史 |
| 闇の部分(その一):中国小説翻訳試論 | 近藤直子 |
| 発達障害者の行動の変容に関する研究[第2報]:施設で問題になる行動の変容に及ぼす要因 | 渡邉映子 宮本文雄 野田幸江 小沼肇 |
| 聴覚障害児の文章読解力について | 中村真理 |
| 20世紀初頭のイギリスにおけるプレパラトリースクールのゲーム活動:イギリス初等・中等教育の学校体育理論との比較史的検討 | 榊原浩晃 |
| 日本列島周辺における海洋プレート上のジュラ:白亜系の移動経路 | 青野宏美 |
| 「商品」における社会関係〔Ⅱ〕 | 日山紀彦 |
| 明治時代語の一側面(4) | 松井栄一 |
| 一茶の手法と川柳の手法 | 江口孝夫 |
| 朝鮮本『天地八陽神呪経』とその流伝 | 増尾伸一郎 |
| 東京成徳大学研究プロジェクト課題(1996年度) |
第3号
出版年:平成8年(1996年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 18世紀イギリス国会の雄弁家たち(2) | 中川誠 |
| スティービー・スミスとウィリアム・ブレイク | 金沢融 |
| Hamletの構成 | 髙山浩子 |
| Imagery and Character in To the Lighthouse | 江澤恭子 |
| 続 わからないこと:書くこと、そして残雪の「それ」をめぐって | 近藤直子 |
| カンプチア・クロム研究序説 | 大橋久利 |
| 心理言語学的に見た言語習得について | 前田洋文 |
| 一貫性と照応関係 | 海老名洸子 |
| 日本人英語学習者による日本語音素/N/の英語音素/n/への転移について | 今仲昌宏 |
| 発達障害者の行動の変容に関する研究 | 渡辺映子 宮本文雄 小沼肇 |
| 入所型福祉施設の社会化過程:Ⅰ.多施設間の比較 | 内田一成 岡田明 |
| 聴覚障害児における助詞の使用についての検討 | 中村真理 |
| 精神薄弱者施設の行動論的レジデンシャル・ソーシャル・ワークに関する組織実験 | 内田一成 |
| 知的障害者(養護学校卒業生)の余暇活動に関する研究:年齢の要因からの分析を通して | 宮本文雄 大野由三 |
| 聴覚障害児の読み研究における新しい動向 | 鄭仁豪 |
| 情報教育と教育情報 | 吉田寛 |
| Earl of Meath の問題提起:19世紀末イギリス初等教育への体育授業導入に関連して | 榊原浩晃 |
| 東京成徳大学周辺の自然環境:八千代市内における太陽紫外線量と自然放射線量の測定 | 青野宏美 金子一郎 西澤利栄 |
| 「商品」における社会関係〔1〕 | 日山紀彦 |
| 「御新造」考 | 大久保恵子 |
| 明治時代語の一側面(3) | 松井栄一 |
| 菅原道真の「奉哭吏部王」の詩について | 菅野禮行 |
| 東京成徳大学研究プロジェクト課題(1995年度) |
第2号
出版年:平成7年(1995年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 18世紀イギリス国会の雄弁家たち | 中川誠 |
| スティービー・スミスのキリスト教観 | 金沢融 |
| 英語発音・発声訓練前後の英語音素の聞き取りの比較について | 前田洋文 堤昌生 今仲昌宏 江澤恭子 |
| 日英語の照応表現の比較 | 海老名洸子 |
| A Study of Cambodian Political Awareness | 大橋久利 |
| 聾学校教員の意識調査:学力 コミュニケーション・モード 教育方法・内容に関連して | 今井秀雄 |
| 教室における児童の愛他行動と攻撃行動並びにその関連について | 高野清純 広田信一 |
| 自閉症児の象徴遊びの形成に及ぼすNDRAの系統的操作の効果 | 内田一成 |
| 聴覚障害児における読書力診断検査に基づく言語指導法の検討 | 中村真理 |
| 説明的文章における聴覚障害児の読みのプロセスに関する研究 | 鄭仁豪 |
| 生活保護の「必要即応の原則」に関する一考察 | 山口春子 |
| イギリス初等教育草創期の drill 論議 | 榊原浩晃 |
| 本学学生の体力測定結果に関する一考察:1994年度報告 | 川北準人 |
| 画像データベースについて | 福山裕宣 |
| 三郡-山口帯東部、鶏足山塊のジュラ系砂岩分析 | 青野宏美 |
| 東京成徳大学周辺の自然環境:大学構内の自然放射線量の測定 | 青野宏美 金子一郎 西澤利栄 |
| 明治時代語の一側面(2) | 松井栄一 |
| 「読むこと」と「書くこと」:フィッシュの読者反応理論とワーズワス | 栗原晶江 |
| 深層心理からみた Hamlet | 髙山浩子 |
| 吃苹果的特権:論残雪的<痕> | 近藤直子 |
| A Study on Virginia Woolf's Mrs Dalloway:Moments of Happiness and Androgynous Qualities | 江澤恭子 |
| 東京成徳大学研究プロジェクト課題(1994年度) |
第1号
出版年:平成6年(1994年)3月15日
| タイトル | 執筆者 |
| 創刊号に寄せて | 木内四郎兵衛 |
| 理性と想像:モンテーニュとハズリットの現代的意義 | 中川誠 |
| 認知スタイルと英文要約について | 前田洋文 堤昌生 桑原和昭 |
| 英語音声変化と調音限界 | 今仲昌宏 |
| MWM式言語インベントリーの標準化(その1) | 岡田明 松原達哉 |
| アメリカにおける知的遅滞者の社会的統合について:イリノイ州における居住の場の調査研究 | 渡辺映子 |
| 潜在性二分脊椎を合併した1軽度精神遅滞成人の尿・便失禁に対する行動療法の効果的適用 | 内田一成 |
| 19世紀末のイギリスにおける体育教員養成問題:Training Collegeの体育事情を手がかりに | 榊原浩晃 |
| 本学学生の体力測定結果に関する一考察 | 川北準人 吉本修 榊原浩晃 |
| 房総半島, 上総層群中の堆積相のクラスタ解析 | 青野宏美 |
| カラー画像と画像圧縮 | 吉田寛 |
| 明治時代語の一側面(1) | 松井栄一 |
| 菅原道真の文学的感興について | 菅野禮行 |
| ことばの夜:文革の笑い話と残雪 | 近藤直子 |
| Hamlet における先王とその亡霊 | 髙山浩子 |
| A Study on Virginia Woolf's To the Lighthouse | 江澤恭子 |
| 東京成徳大学研究プロジェクト課題(1993年度) |