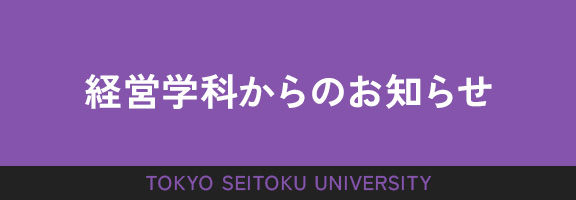経営学科 授業紹介
Pick Up!
キャリアデザインⅢ

コミュニケーションスキルを活かし
チームワークの最大化に貢献
1泊2日の小田原ビジネス実習では「広報・宣伝の企画実習」をテーマに、私たちのグループは小田原市観光協会を取材しました。その日のうちに内容をまとめ翌日にプレゼンを行うため、率先して声をかけチームワークを強化するとともに、意見しやすい雰囲気づくりを意識しました。
チームワークの最大化に貢献
1泊2日の小田原ビジネス実習では「広報・宣伝の企画実習」をテーマに、私たちのグループは小田原市観光協会を取材しました。その日のうちに内容をまとめ翌日にプレゼンを行うため、率先して声をかけチームワークを強化するとともに、意見しやすい雰囲気づくりを意識しました。
Pick Up!
トラベル・ホスピタリティ・ビジネス論

プレゼンテーションスキルを高め
就職活動のアピールポイントに
トラベル・ビジネスにおけるホスピタリティの重要性を学びました。授業では実際にツアーを考案する課題もあり、私たちのグループはイタリアのパッケージツアーを企画しました。授業で学んだ効果的なビジネス・プレゼンテーションの手法を活用した発表ができました。
就職活動のアピールポイントに
トラベル・ビジネスにおけるホスピタリティの重要性を学びました。授業では実際にツアーを考案する課題もあり、私たちのグループはイタリアのパッケージツアーを企画しました。授業で学んだ効果的なビジネス・プレゼンテーションの手法を活用した発表ができました。
ゼミナール
ゼミナール(通称ゼミ)は大学教育の中で特に重要な科目です。なぜなら、一般の講義と異なり、ゼミでは学生が主体となって少人数で運営され、指導教員より親身の指導をうけることができるからです。また、ゼミ活動の集大成である卒論は、学生にとって大学での学びの中核と位置づけられます。
ゼミ活動は、テーマ設定、調査・研究、発表、ゼミ仲間との議論等が基本ですが、実はこうした取組みは学生が社会に出て様々な仕事をする場合の仕事の手順とかなり似たものです。ゼミに真摯に取組むことで、学生はスムーズに社会に出て活躍することができます。
ゼミ活動は、テーマ設定、調査・研究、発表、ゼミ仲間との議論等が基本ですが、実はこうした取組みは学生が社会に出て様々な仕事をする場合の仕事の手順とかなり似たものです。ゼミに真摯に取組むことで、学生はスムーズに社会に出て活躍することができます。

- 「コミュニティビジネス」の鈴木ゼミナール
- 「管理会計」が研究テーマの布川ゼミナール
- 「ファッションビジネス」が研究テーマの芳野ゼミナール
- 「産業心理」を研究する池田ゼミナール
- 「都市観光」が研究テーマのゼミの原田ゼミナ-ル
- 「会社史」を研究する伊藤ゼミナール
- 「サプライチェーン・マネジメント」を学ぶ樋口ゼミナール
- 「情報システム」を学ぶ石川(正)ゼミナール
- 「企業の不祥事」を研究する石川(雅)ゼミナール
- 「公益事業」の今後のあり方を研究する武井ゼミナール
- 「財務会計」を研究する中井ゼミナール
- 「イノベーション・マネジメント」を研究する宮澤ゼミナール
- 「マーケティング」を学ぶ德永ゼミ
- 「エンターテインメントビジネスとクリエイティビティ」を研究する板生ゼミ
簿記原理

簿記とは、事業の共通言語である会計の数値を算出するための技法です。複式簿記の基礎理論および基本的手続、個別論点や決算整理手続など、商業簿記における財務諸表の作成を学びます。
エンターテインメント・ビジネスの消費者行動

経営学全般に共通する理論や考え方を紹介しながら、エンターテインメントビジネス特有のビジネス構造、グローバル競争などを考慮した経営戦略分析を行います。自ら考え、意見を持てる人材を育成します。
インターンシップ

さまざまな企業の実態を学んだあと、約2週間の就業体験を行います。
写真:ラジオ局レインボータウンエフエム放送株式会社様ご協力のもと、経営学部生がインターンシップ体験を話す「東京成徳 チアラジ!」を放送しています。
写真:ラジオ局レインボータウンエフエム放送株式会社様ご協力のもと、経営学部生がインターンシップ体験を話す「東京成徳 チアラジ!」を放送しています。
広報・広告論

マーケティング活動のなかでの広告、販売促進、人的販売、広報など、それぞれの事例を交えて学修します。どのような組み合わせが効果的なマーケティング手法か、基本的な考えを学びます。
経営戦略論

企業経営にあたっては、長期の見通しのもとに綿密な計画を策定する必要があります。さまざまな戦略の具体例や理論を学びます。
経済学入門(マクロ経済)

経済学は私たちの生活に密接に関わっており、経済の状況を知るためにはさまざまな指標があります。この授業では、それらの指標やマクロ経済学の考え方について学び、経済の本質を見抜くための力を養います。
トラベル・ホスピタリティ基礎

私たちに身近な産業である観光を体系的に学ぶ授業です。観光の歴史、サスティナブル・ツーリズムについて、世界の宗教と文化など、いろいろな切り口から「観光とは何か」を読み解いていきます。
ファッション実技(縫製基礎)

アパレル業界のさまざまな職種(デザイナー、販売など)で共通して必要となる基礎知識と、簡単な縫製技術を身につけます。
写真:これまでに学んだ縫製技術を活かして、自分だけの一着をつくっています。
写真:これまでに学んだ縫製技術を活かして、自分だけの一着をつくっています。